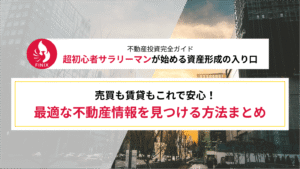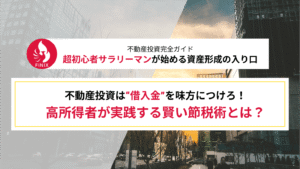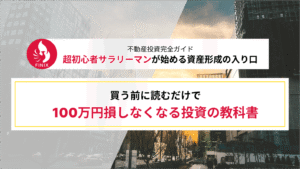不動産投資は、節税対策や安定収入を狙う手段として、特に高所得のサラリーマンや経営者に人気を集めています。しかし、実際に物件を保有し始めてから多くの投資家が直面するのが「入居者トラブル」。
家賃滞納や夜間騒音、無断退去など、トラブルの種類は多岐にわたり、対応を誤ると収益に大きな影響を及ぼす可能性も。
本記事では、実際にあった入居者トラブルの具体例から、トラブルを未然に防ぐための管理方法や対策、信頼できる管理会社の選び方まで、実践的な情報をわかりやすく解説します。
これから不動産投資を始める方も、すでに物件をお持ちの方も必見の内容です。
なぜ「入居者トラブル」が不動産投資のリスクになるのか?
不動産投資において、賃貸物件の管理は収益を左右する極めて重要な要素です。特に、入居者トラブルの発生は、家賃収入に影響を及ぼすだけでなく、信頼関係の崩壊や長期的な経営悪化につながる可能性があります。
たとえば、家賃滞納や原状回復をめぐる退去時のクレーム、近隣との騒音トラブルなど、いずれもオーナーの対応ひとつで「収益を守る」か「損害を被る」かが分かれます。特に管理会社に委託している場合でも、すべてを任せきりにするのではなく、問題の把握と適切な判断が求められるのです。
入居者トラブルが不動産経営に与える主な影響
- 収益の減少
家賃滞納が続けば、オーナーの収入は直撃されます。保証会社の加入がある場合でも、免責期間や条件付き保証となっているケースもあるため注意が必要です。 - 原状回復費用の増大
退去時にトラブルがあると、敷金だけでまかなえない修繕費が発生する可能性があります。とくに破損・カビ・水漏れ・不具合などの設備問題があると、請求額が高額になることも。 - 時間と労力の浪費
トラブルが発生すると、電話やメールでの連絡対応、通知書の送付、裁判や強制執行手続きの準備など、膨大な業務が発生します。これは経営の効率を大きく下げる要因です。 - 近隣住民や他の入居者への悪影響
騒音やゴミ出しなどの迷惑行為が放置されると、他の賃借人の退去や評判の低下に直結します。結果的に空室が増え、収益性が落ちるという悪循環に。
想定外のトラブルに備える「管理体制」がカギ
入居者とのトラブルは、必ずしも回避できるものではありません。しかし、事前に契約書に明記し、ルールを設定し、トラブル発生時の対応フローを決めておくことで、被害を最小限に抑えることが可能です。さらに、弁護士や専門家に相談できる体制を整えることも重要です。
なぜトラブルが起きるのか?その根本原因を知る
多くのトラブルは、以下のような「小さなほころび」から発生します。
- 契約書の内容が曖昧、もしくは説明不足
- 住環境に関するルール(騒音・ゴミ出しなど)の事前通知がない
- 審査が甘く、問題を起こしやすい入居者を受け入れてしまう
- 管理会社との情報共有が不十分で、対応が遅れる
- 設備の老朽化により、継続的な修繕が必要になっている
「入居者トラブル」は想定しておくべき経営課題
不動産経営は、収益を得るという目的の裏側に、居住者との関係性を築くという義務が存在します。トラブルを未然に防ぐことが理想ですが、実際には発生した際の「対処法」と「再発防止策」こそがオーナーの真価を問われるポイントとなります。
よくある入居者トラブルと実際の事例
不動産の現場では、賃貸借契約書でルールを定めていても、さまざまな入居者トラブルが発生します。ここでは、実際に頻繁に起こるケースを分類し、それぞれの原因・対処法・改善策を含めて具体的に解説します。
1. 家賃滞納・支払い遅延
最も多いのが、家賃の滞納や遅延です。これは経営に直接的な影響を与える重大な問題です。
発生事例:
30代単身男性の入居者が、1カ月の遅延を何度も繰り返し、最終的には3カ月分の滞納に発展。保証会社があったため一定の支払いは受けられたが、督促・通知・契約解除手続き・明け渡し請求・原状回復費用の回収に数カ月かかり、オーナーの負担が大きかった。
原因:
- 本人の収入減少や失業
- 支払いに対する意識の甘さ
- 保証人や保証会社との契約が不十分
対策:
- 契約時の審査強化(収入証明、勤務先確認)
- 保証会社の加入を義務化
- 支払い遅延時の対応フロー(催告・内容証明の送付・弁護士への依頼)を明確に定める
2. 騒音・迷惑行為・ゴミ出し
次に多いのが、生活マナーの違反や近隣住民とのトラブルです。
発生事例:
アパート1階に住む高齢者から、2階の若者による「深夜の音楽・ドタバタ音・友人の出入り」が激しいと苦情が相次いだケース。対応が遅れたことで高齢者が退去し、他の入居希望者も敬遠する結果に。
原因:
- 騒音やゴミのルールを契約書に記載していない
- 入居時の説明が不十分
- ルール違反を放置してしまう管理体制の甘さ
対策:
- 契約書に「受忍限度を超える騒音は禁止」と明記
- ルールブックや注意喚起文書を作成・送付
- 録音や動画などの証拠収集を促す
- 注意しても改善されない場合は契約解除も視野に
3. ペットの無断飼育・禁止事項違反
ペット飼育不可の賃貸物件で無断飼育が発覚する事例も少なくありません。
発生事例:
「ペット禁止」と契約書に明記していたにもかかわらず、猫の飼育が近隣住民からの苦情で発覚。フローリングの傷や臭いによる原状回復費用として敷金以上の請求が必要となったが、入居者は支払いを拒否し、裁判で争う事態に。
原因:
- 契約違反に対する罰則規定が曖昧
- 管理会社による定期確認がなかった
- 飼育状況の把握が遅れた
対策:
- 「違反時は契約解除可能」と特約で明記
- 退去時にかかる修繕費用の上限・範囲を契約書に記載
- 発覚時は即座に本人へ通知し、合意解除を検討
4. 退去時の原状回復・修繕費用トラブル
退去時のトラブルも非常に多く、特に費用負担や契約解除の理由をめぐる紛争が頻発します。
発生事例:
7年間居住した後、原状回復費として20万円以上を請求したところ、入居者が「経年劣化なのに不当」と主張。結果として弁護士を通じて交渉、国土交通省のガイドラインに沿った妥当な範囲で再計算し、和解が成立。
原因:
- 経年劣化と故意・過失による破損の線引きが曖昧
- 契約書に明確な費用負担の規定がない
- 記録や証拠が不足
対策:
- 入居時と退去時に室内の状態を写真や動画で記録
- ガイドラインに基づいた原状回復費の説明書を作成
- 内容証明などで書面によるやりとりを行う
5. 無断退去・連絡が取れないケース
本人と連絡が取れず、放置されたままの部屋が残されるというケースもあります。
発生事例:
40代男性の単身入居者が数カ月分の家賃を滞納し、そのまま連絡が取れず。部屋には家具や衣類が放置されており、強制執行の手続きが必要になった。
原因:
- 緊急連絡先や連帯保証人の連絡網が不十分
- 滞納時の対応マニュアルがない
- 任意の合意解除ができず、法的手段に頼るしかない
対策:
- 契約書に「連絡不能時の対処」に関する条項を明記
- 弁護士や司法書士と連携し、手続きの段階を確認
- 管理会社と協力して速やかに対応
入居者トラブルの「原因」と「予防策」
不動産経営における入居者トラブルは、突発的に起こるものではなく、多くが「事前に防げた問題」であることが少なくありません。ここでは、そうしたトラブルが発生する根本的な原因と、それに対する実践的な予防策を解説します。
1. 契約書・特約の不備や説明不足
多くのトラブルの原因が、賃貸借契約書の内容が不明瞭、または重要事項の説明が不足していることにあります。
具体的な問題点:
- 騒音、ペット、ゴミ出しなどの生活ルールが曖昧または未記載
- 原状回復の費用負担範囲が明確でない
- 退去予告や契約解除の手続きが不十分
- 違反行為に対する対応策が記載されていない
予防策:
- 国土交通省のガイドラインに基づいた契約書の作成
- 特約(例:ペット禁止、楽器使用不可)を詳細に記載
- 契約時に「重要事項説明」として丁寧に説明する時間を確保
- 借主・連帯保証人の署名・捺印を得ることで、認識の証拠を残す
契約時の説明が不十分なまま入居が始まると、後になって「そんな話は聞いていない」と主張されるリスクが高まります。
2. 入居前審査の甘さ
入居者選定の段階で適切な審査を行わなかった場合、後のトラブル発生率は格段に高くなります。
よくあるミス:
- 収入や職業を十分に確認せずに契約
- 緊急連絡先や連帯保証人が形だけで機能していない
- 過去の家賃滞納や退去トラブルの履歴を把握していない
予防策:
- 収入証明・勤務先確認・本人確認資料の厳格な審査
- 保証会社の加入を原則とし、信用スコアを確認
- 過去のトラブル事例がある場合は入居を再検討
- 審査結果の記録を保管し、万一のトラブルに備える
また、外国籍や学生など特殊なケースでは、本人確認や支払能力の確認方法を変える必要があります。
3. 管理体制の不備と対応遅れ
オーナーや管理会社の対応が遅れることでトラブルが悪化するケースも多く見受けられます。
典型的な状況:
- クレーム対応を放置し、近隣住民から訴訟や退去要求
- 設備の故障(給湯器・エアコン・水漏れなど)に対する対応が遅れる
- ゴミ出しのマナー違反や放置自転車など、建物全体の環境悪化
予防策:
- 管理会社と定期報告・情報共有体制を構築
- 対応マニュアルを整備し、時間単位での行動基準を明記
- 建物の清掃・点検を定期的に実施し、老朽化への対応を怠らない
- 入居者アンケートなどで日常の不満を把握し、事前対応に努める
「放置された小さな問題」は、やがて裁判や損害賠償請求に発展することもあるため、未然の対処が最も重要です。
4. ルール・マナーに対する意識の差
入居者の中には、「住まいは単なる一時的な居場所」として捉えており、共用部分や近隣住民に対する配慮を欠く行動をとることもあります。
例:
- 深夜のテレビ音量や音楽演奏
- 階段や共用廊下への私物放置
- 無断駐車・自転車の無断設置
- 室内でのDIYや禁止行為(火気使用・ヒーター改造など)
予防策:
- 入居時に「生活ルール」を書面で交付
- ルール違反が発覚した際の通知文・警告文テンプレートを用意
- 再三の注意でも改善されない場合は契約解除の可能性を明記
トラブル発生の可能性を下げるためには、事前の教育と定期的な注意喚起が不可欠です。
トラブル発生時の対応フローと注意点
入居者トラブルが実際に発生した場合、冷静かつ迅速な対応が不可欠です。特に、感情的な対立や誤った対応はさらなるトラブルを招き、損害や法的責任を拡大させるリスクがあります。ここでは、一般的な対応フローと各ステップでの注意点を整理して解説します。
1. 事実確認と証拠の収集
第一にやるべきことは「正確な事実の把握」です。管理会社や近隣住民からのクレーム、入居者本人からの主張があった場合も、感情的な判断を避け、客観的な証拠に基づいて状況を整理します。
主な手段:
- 騒音:録音、動画、日時の記録
- ゴミやペット:写真、現場確認のメモ
- 家賃滞納:支払履歴、請求書控え、賃貸借契約書の該当条文
- 室内破損:現地写真、修理業者の報告書
- 水漏れや設備故障:修理記録、交換部品の証明
注意点:
- 証拠は書面・画像・録音など形に残るものを優先
- 当事者双方の言い分を公平に聴く姿勢を持つ
- 記録は必ず時系列で整理する(後の訴訟時にも有効)
2. 初期対応と連絡の取り方
状況が明らかになったら、関係者への連絡と初期対応に移ります。ここで重要なのは、感情的な言い争いを避けること、そして記録に残る形でやり取りすることです。
連絡方法の基本:
- 電話で連絡 → 書面で通知(郵便・内容証明)
- LINEやSNSではなく、メールや書面で残す
- 連帯保証人にも同時に連絡し、現状を共有
初期対応のポイント:
- 家賃滞納の場合:支払督促状を送付し、期日を明記
- 騒音・迷惑行為の場合:注意喚起文を掲示・個別送付
- 修繕対応の場合:故障の詳細と修繕予定を明記した案内を送付
重要なのは「通知を送ったという証拠を残すこと」です。内容証明郵便を使うと、後に裁判となった場合でも有効な証拠になります。
3. 解決に向けた交渉・改善要請
通知や注意喚起の後も状況が改善しない場合、本人や連帯保証人と直接交渉に入る必要があります。
交渉時のコツ:
- 感情ではなく、契約書と事実を根拠に話す
- 相手の言い分にも耳を傾けることで「一方的」にならない
- 言質を取るために、話し合いの内容は録音・議事録に残す
改善要求の伝え方:
- 期限付きで改善要請を出す(例:「1週間以内に対応しない場合は契約解除手続きに移行」)
- 第三者(管理会社や弁護士)を交えた話し合いの場を設ける
- 改善が見られた場合は記録として保存し、経過観察を継続
4. 契約解除・退去手続きへ進む際の注意点
改善が見込めない、または重大な契約違反が確認された場合、契約解除や強制退去の判断が必要になります。
手順:
- 契約書の「解除条項」や「違反時の対応規定」を確認
- 契約解除通知書を内容証明で送付
- 合意解除を求める場合は「退去合意書」の作成を検討
- 明渡しがない場合は、裁判所への明渡請求訴訟・強制執行の申立て
注意点:
- 法的には正当な理由が必要(民法や判例に基づく)
- 合意解除が成立すれば、訴訟を回避可能
- 強制退去の場合、費用負担や時間的コストも考慮
契約解除は最終手段ですが、放置して時間が経つほど、空室リスクや修繕費用の増加に繋がります。オーナー側が毅然とした対応を取ることが重要です。
信頼できる管理会社の選び方と委託のメリット
不動産投資におけるトラブル対応の成否は、管理体制の質に大きく左右されます。特に多忙なオーナーや、複数の賃貸物件を所有している事業者にとって、管理業務を信頼できる管理会社に委託することは、収益の安定化とリスクの低減に直結します。
ここでは、適切な管理会社の選び方と、委託することで得られる具体的なメリットについて解説します。
1. 管理会社選びのチェックポイント
多くの不動産業者が管理業務を請け負っていますが、どこでも良いというわけではありません。管理会社によって、対応力・費用・業務範囲・トラブル解決能力に大きな差があります。
選定時のポイント:
- 対応スピードと連絡体制
緊急時(騒音・水漏れ・設備故障など)に、即座に動ける体制かを確認します。24時間対応の有無や緊急ダイヤルの設置などが明確かが重要です。 - 入居者対応の実績とトラブル解決経験
迷惑行為・家賃滞納・原状回復などの対応事例が豊富か。具体的な解決策や過去の対応方法を聞き、判断します。 - 報告・書類の正確性と記録管理能力
クレームや対応履歴を記録・報告してくれる体制があるか、また書面で報告書や通知文書を作成してくれるかもポイントです。 - 管理費用の明確さ
業務内容に対する報酬(賃料の〇%、固定費など)が妥当かつ明確に記載されているか。また、追加料金が発生するケース(立ち退き・訴訟対応・設備交換など)も確認しておきます。 - 国土交通省のガイドラインや賃貸住宅管理業法に準拠しているか
法令遵守の姿勢が明確であることは信頼性の証拠です。
2. 委託によるメリット
不動産オーナーが自己管理をする場合、時間・知識・対応スキルが問われます。一方、管理会社に業務を委託することで、以下のような多くのメリットがあります。
主なメリット:
- トラブル初期対応の迅速化
入居者や近隣住民からのクレームを、管理会社が一次対応し、状況に応じてオーナーへ報告してくれるため、感情的対立を防げます。 - 専門的な知見を持ったスタッフが対応
民法や賃貸借契約、損害賠償の知識を有する担当者が、通知・交渉・書類作成などの実務を代行。万一の場合も、弁護士などと連携しやすくなります。 - 空室対策・入居者募集のプロセスも一任可能
入居者の審査・書面作成・更新手続き・広告掲載など、全体の業務を一貫して依頼できるため、時間と労力を大幅に削減できます。 - 建物の設備保守・修繕にも対応
給湯器・エアコン・配管などの老朽化に伴う交換・修繕のスケジュール管理、費用見積もりの提案なども行ってくれるため、突発的な費用負担を抑える効果もあります。 - 契約書や通知書の作成代行
賃貸借契約書、更新合意書、契約解除通知などの正確な書類作成が可能。法的な誤りがあった場合の無効リスクも軽減されます。
3. 委託契約時の注意点とリスク管理
ただし、すべての管理会社が完璧とは限りません。契約時には以下のようなリスク管理も必要です。
注意点:
- 業務範囲を明記した管理委託契約書の締結
どこまでが管理会社の責任か(例:修繕費の見積もり承認、契約解除の判断など)、役割分担を明確に記載することが重要です。 - 報酬や追加料金の条件を具体的に記載
設備修理、強制執行、裁判対応などで別途費用が発生するケースの取り決めを契約書に記載しておきましょう。 - 契約期間と更新・解約条件を確認
解約の予告期間、違約金の有無、契約更新の自動継続の条件もチェックすべきポイントです。 - 管理品質が低い場合の対処フロー
対応が遅い、報告がない、誤対応があった場合などに備え、契約解除や管理変更のルールを事前に取り決めておくことがリスク回避につながります。
入居者との契約・退去・明け渡しまでの流れ
不動産投資における賃貸経営では、入居者との契約から退去までの一連の流れを、法的根拠に基づき、適切に管理することが求められます。ここでは、入居前の契約手続きから、退去・明け渡し・原状回復に至るまでの実務と注意点を解説します。
1. 賃貸借契約締結時の注意点
契約時のミスや曖昧な合意は、トラブルの火種になります。特に契約書の内容は、民法や判例、国土交通省のガイドラインに即して、具体的かつ妥当な内容であることが求められます。
主な注意点:
- 賃貸借契約書には家賃・敷金・契約期間・解約条件・禁止事項などを明記
- 保証会社加入の義務化と、連帯保証人の適正な設定
- ペット・楽器・DIY・複数人入居などに関する特約の追加
- 契約書には、退去時の原状回復範囲、修繕費用の負担割合を明記
契約期間・更新料・解約予告・違約金・退去時費用などの「金銭に関わる項目」は、特に明確に記載する必要があります。
2. 入居中の契約維持と信頼関係の管理
契約後も、入居者と良好な信頼関係を維持し、生活環境や物件の維持管理を適切に実施することが重要です。
定期的な業務:
- 建物や共用部の点検、清掃の実施
- 設備の故障(給湯器・照明・エアコンなど)への迅速な修理対応
- 更新時の再契約・更新料・契約内容の確認
- クレームや苦情(騒音・ゴミ出し・駐車など)の受理と対処
信頼関係の悪化は、契約解除や訴訟の原因となるため、連絡体制や記録の徹底が必要です。
3. 解約・契約解除とその理由
入居者からの解約、またはオーナー側からの契約解除には、それぞれ法的手続きと「正当な理由」が必要です。
入居者からの解約:
- 原則として1カ月前の解約予告が必要(契約書により定める)
- 原状回復義務・鍵返却・立会いの実施が必要
オーナー側からの解除:
- 家賃滞納(一定期間・回数)
- 重大な契約違反(ペット無断飼育・迷惑行為の継続)
- 明け渡し請求には、正当な理由と「通知書・内容証明郵便」などの証拠が必要
- 合意解除が得られない場合は、裁判所を通じて「明渡し請求訴訟」や「強制執行」に進むことも
注意点:
- 解約トラブルが発生しやすいため、契約書に「解除条件」や「手続き方法」の記載が不可欠
- 書面での通知、記録の保存、弁護士との連携が有効
4. 退去時の原状回復と費用精算
退去時には、原状回復費用の請求や敷金の返還など金銭的な処理が必要になります。
主な流れ:
- 室内の確認・立会い
- 傷・破損・汚損の有無の記録(写真・動画)
- 修繕費の見積り作成
- 貸主・借主双方で確認し合意書を作成
- 敷金の返還と差額の清算(請求または返金)
注意点:
- 経年劣化(フローリングの変色、壁紙の自然な退色)と故意・過失による破損は区別する
- 国土交通省の原状回復ガイドラインに従うことで、過剰請求や法的トラブルを回避
- 明確な記録(写真・書面・費用明細)を残すことで、紛争防止に役立つ
トラブルが発生した場合の対応:
- 支払い拒否がある場合は、内容証明の送付や少額訴訟の検討
- 専門家(弁護士・司法書士)と連携した対応が望ましい
入居者トラブルを未然に防ぐためのガイドライン
入居者トラブルの多くは、「想定不足」と「情報不足」により発生します。発生してからの対応も重要ですが、トラブルを未然に防ぐための体制づくりこそが、安定した賃貸経営の基盤となります。
ここでは、ルールの明文化・入居者教育・建物環境の整備など、「予防」のための具体策を解説します。
1. 入居時にルールを明示する
入居者とのトラブルを避けるには、最初の段階で明確なルールを伝えることが重要です。
推奨される取り組み:
- 「入居者ルールブック」の作成と配布
騒音・ゴミ出し・共用部の使用・ペット禁止・禁止行為など、生活上のルールを一覧にまとめた書面を渡すことで、認識の違いを未然に防げます。 - 契約書・重要事項説明書への記載強化
曖昧になりがちなマナーや生活態度に関する事項を、契約書に明確に記載することで、契約違反への対応が容易になります。 - 書面による署名捺印の取得
内容に同意した証拠を残すことで、将来的な争いを予防できます。 - 保証会社との連携でリスク低減
滞納リスクに備えて、入居時の与信審査や支払い能力の確認を徹底することが重要です。
2. 定期的な注意喚起と情報提供
トラブル防止には、継続的なコミュニケーションが不可欠です。
有効な手段:
- 共有部分への掲示物(騒音・ゴミ分別・駐輪など)
- 月1回の「暮らしのマナー通信」などの配布
- 迷惑行為が発覚したときの「全戸への注意喚起文書」
入居者は、自分の行動が周囲に迷惑をかけていると気付いていないケースが多いため、注意喚起のきっかけが必要です。
3. 建物設備・共用部分の維持と整備
設備や建物の老朽化が進むと、クレーム・トラブルの発生率が上昇します。オーナー側が定期的な修繕・改善を実施することも、入居者満足度の向上とトラブル抑制に繋がります。
具体的な施策:
- 老朽化設備(給湯器、トイレ、エアコンなど)の定期点検と交換計画
- 共用部の清掃・照明交換・防犯カメラ設置
- 防音対策(床材・壁材の強化、遮音カーテンの案内)
- 雨漏り・水漏れ・カビの早期発見と修理
物件価値の維持にもつながり、長期的な入居者の定着や空室率の低下にも寄与します。
4. 近隣住民・地域社会との連携強化
迷惑行為の苦情やトラブルは、近隣住民や自治体との関係性によっても変わります。
効果的な方法:
- 町内会や自治会との情報共有
- 地域清掃活動への協力・参加
- 近隣からのクレーム受付体制の構築(管理会社の窓口設置)
近隣からの信頼を得ることで、苦情の早期把握や、解決への協力も得やすくなります。
5. 管理会社と協力して、事前対応を仕組み化する
最後に、トラブル予防策はオーナー1人では限界があります。
管理会社や専門家と連携し、対応ルールを仕組み化することで、持続的かつ効果的な対策が可能となります。
具体的な仕組み例:
- トラブル対応マニュアル(通知→改善要請→解除検討)
- クレーム記録の共有システム
- トラブル多発物件の改善会議(管理会社・オーナー・専門家で構成)
- ガイドラインに基づく書類テンプレート(注意文書、解除通知、明け渡し請求など)
まとめ|トラブル対処も「不動産経営力」の一部
「トラブルが多い物件」というイメージがついてしまうと、入居率が下がり、空室が続く原因になります。反対に、迅速で的確な対応を行う管理体制が整っている物件は、入居者からの信頼を得て、長期的な居住にもつながります。
また、対応が誠実であることは、近隣住民や地域からの評価にも直結し、トラブルが発生してもスムーズな協力が得られる環境を生み出します。
不動産投資における収益の最大化は、「満室経営」だけではありません。トラブルに強い体制づくりと、トラブル対応の質を高めることが、結果的に賃料収入の安定と長期的な資産価値の維持につながります。
3. 不動産投資は「事業」だという意識を持つ
最後に強調したいのは、不動産投資は「単なる副収入」ではなく、れっきとした事業活動であるという点です。
事業には、次のような構成要素があります。
- 顧客との契約管理(賃貸借契約)
- 商品(物件)の品質管理(建物・設備の維持)
- トラブル対応・カスタマーサポート(クレーム・苦情処理)
- 資金繰りと費用対効果(修繕費・管理費・税務)
- リスク管理と法務(契約解除、訴訟対応、債務不履行時の処理)
これらを一つひとつ丁寧に行うことで、単なる「物件オーナー」ではなく、真の「不動産事業者」として信頼される存在になることができるのです。